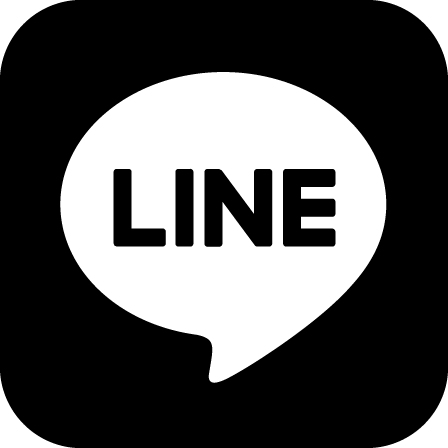子象は小さな杭につながれて育ちます。幼い頃は抜けませんが、成長して力がついても「どうせ抜けない」と挑戦をやめてしまう——この比喩が「エレファント・シンドローム」です。心理学では“学習性無力感”とも呼ばれ、過去の失敗体験が現在の行動を縛ってしまう状態を指します。
私たちの日常でもよく起こります。
「運動は続かないタイプだから」「ダイエットは何度やっても無理」「腰が痛いから歩けない」——これらは“事実”ではなく“解釈”です。たとえば「先週の体操は3回しかできなかった」は事実ですが、「自分は意志が弱い」は解釈。解釈を事実だと思い込むと、鎖はどんどん太くなります。
では、どう外すか。ポイントは“とても小さく、具体的に”です。
-
・事実と解釈を分ける
紙に2列作り、左に数値で書ける事実(回数・時間・痛みスコア)、右に頭の中の声(不安・決めつけ)を書き出します。見える化すると、絡まった糸がほどけます。・反証を3つ探す
「続かない」と思ったら、過去1週間で“できたこと”を3つ挙げましょう。1回でもやれた日は、すでに反証です。・1センチ行動
最小単位まで分解します。例:朝の椅子ストレッチ20秒、歯みがき前のドローイン30秒、エレベーター前で姿勢リセット10秒。達成感が次の行動を呼びます。・IF-THENプラン
「もしAなら、Bをする」と決め打ち。
IF 朝こわばる → THEN 椅子で体幹20秒
IF 仕事の合間にため息 → THEN 肩回し5回
迷いを減らすことで、行動のスイッチが軽くなります。・成功ログ
手帳やスマホに○×をつけるだけでOK。週1回見返し、○が並んだら自分を褒める。自己効力感(やればできる感覚)が少しずつ育ちます。注意点として、医療用語の象皮病(Elephantiasis)や映画で有名なプロテウス症候群(俗に「エレファント・マン病」)とはまったく別物です。ここで扱うのは“心のクセ”の話。身体の症状が強い場合は、医療機関での評価を併用しましょう。
最後に。鎖は一気には外れません。でも、今日の“1センチ”で十分です。明日のあなたは、今日より少しだけ自由。まずはこのブログを読み終えたら、深呼吸ひとつと肩回し5回——そこから始めてみませんか。