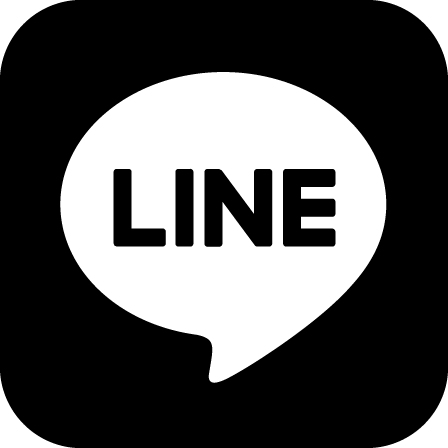「動かないと筋肉が細くなる」ことは、多くの人が知っています。でも実は、筋肉だけでなく関節の中にある“軟骨”も、動かさないと弱ってしまうのです。この現象を「廃用性萎縮(はいようせいいしゅく)」と呼びます。
関節軟骨の役割
関節軟骨は、骨と骨の間にある薄いクッションのような組織です。弾力があり、骨同士がぶつからないようにしてくれます。そのおかげで、私たちはスムーズに歩いたり、しゃがんだりすることができます。
軟骨の特徴は「血管が通っていない」こと。普通の組織は血液から栄養をもらいますが、軟骨はそうはいきません。関節を動かすことで関節液が流れ、その中から栄養や酸素を受け取っているのです。つまり、動かすこと自体が“栄養補給”になっているのです。
動かさないとどうなる?
体を動かさずにいると、関節軟骨はだんだん薄くなり、質も落ちてしまいます。これは動物実験でも確かめられていて、4週間体重をかけない状態にしただけで軟骨が目に見えて弱った、という報告もあります。筋肉が「使わないと細くなる」ように、軟骨も「使わないとしぼむ」。これが廃用性萎縮です。特徴的なのは、細胞そのものはまだ生きていること。完全に壊れるのではなく、元気をなくした状態といえます。だからこそ、適切に動かすことで回復の可能性があるのです。
関節に必要なのは「荷重」と「運動」
軟骨にとって大事な刺激は大きく分けて2つあります。
荷重(体重がかかること)
立ったり歩いたりすることで関節に圧がかかり、軟骨に刺激が伝わります。
運動(関節を動かすこと)
曲げ伸ばしの動きによって関節液が循環し、栄養が運ばれます。
研究では「動かさないこと」による悪影響の方が、「体重をかけないこと」よりも強いことも示されています。つまり、寝たきりで関節を固定してしまうよりも、軽くでも動かす方が関節には良い影響を与えるということです。
回復の可能性
筋肉や骨は、再び動かせば元に戻ることが知られています。関節軟骨についても同じように、適切な運動や体重負荷をかけることで回復できるのではないかと考えられています。実際に「運動をすると軟骨が修復する力を発揮する」という報告もあり、運動療法の重要性が改めて注目されています。
まとめ
-
関節軟骨は血管から栄養をもらえず、動かすことで健康を保っている。
動かさないと「廃用性萎縮」によって軟骨が薄く弱りやすくなる。
軟骨にとっては「荷重」よりも「関節を動かすこと」の方が大切。
適度な運動で軟骨が回復する可能性がある。
関節を守るためには「じっと安静」よりも「無理のない範囲で動かす」ことが大切です。日常生活の中でこまめに体を動かすことが、関節の健康を保つ一番の秘訣といえるでしょう。