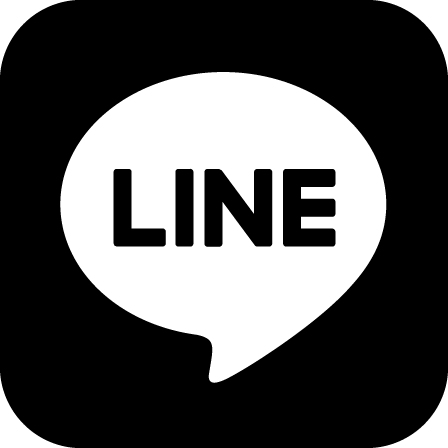私たちの体は「使うことで健康を保つ」ようにできています。例えば、長い間寝たきりでいると筋肉が細く弱ってしまいますよね。これは「廃用性萎縮(はいようせいいしゅく)」と呼ばれる現象です。実はこの現象は筋肉だけでなく、関節の中にある「軟骨」にも起こることがわかっています。
軟骨が弱ってしまう理由
関節軟骨は、骨と骨の間にあるクッションのような役割を果たしており、摩擦を少なくしてスムーズに動けるようにしています。この軟骨は血管から栄養をもらっているわけではなく、関節を動かすことで循環する“関節液”から栄養を受け取っています。
つまり、動かさなかったり体重をかけなかったりすると、栄養や刺激が足りなくなり、徐々に軟骨が薄く弱ってしまうのです。まさに「使わないと衰える」という現象が関節でも起きるのです。
研究でわかってきたこと
動物実験では、後ろ足に体重をかけさせない状態を4週間続けると、関節軟骨が薄くなり質も落ちることが確認されています。ただし、軟骨の細胞自体は生きているため、完全に壊れてしまうわけではありません。いわば「しぼんだ状態」になるのです。
この変化は筋肉が細くなるのと同じように、軟骨も「使わないと衰える」ということを示しています。そして適切に体重をかけたり動かしたりすることで回復できる可能性があると考えられています。
変形性関節症とのつながり
高齢者に多い「変形性関節症(OA)」は、軟骨がすり減り、関節が変形して痛みや動きにくさを起こす病気です。一度進行してしまうと元に戻すのは難しく、予防が非常に大切とされています。
最近の研究で、廃用性萎縮によって弱った軟骨は、普通の軟骨よりも負担に耐えられず、変形性関節症に進みやすいことがわかってきました。つまり、「長期間動かさない → 軟骨が弱る → 急に負担をかけると関節症が進む」という流れが起こりやすいのです。
入院や安静が続いたあとに立ち上がる、歩き出すといった場面では特に注意が必要になります。
関節を守るためにできること
関節を守るカギは「適度に動かすこと」です。軽い歩行やストレッチ、体重をかけた軽い運動は、軟骨に栄養を届け、健康を保つ役割を果たします。これは「関節に油をさすようなイメージ」に近いでしょう。
また、体重管理も重要です。体重が増えすぎると膝や股関節に余分な負担がかかり、軟骨が消耗しやすくなります。逆に痩せすぎて筋肉が落ちてしまうのも、関節を守る力を弱めてしまいます。
つまり、「ほどよく体を動かすこと」「体重を適正に保つこと」が、関節を守る最も効果的な方法といえるのです。
まとめ
廃用性萎縮とは「使わないことで体の組織が弱っていく現象」であり、筋肉だけでなく関節の軟骨にも起こります。動かさないことで軟骨は薄く弱り、変形性関節症につながるリスクが高まります。
しかし、適度な運動や体重管理を心がければ、関節を守り、健康を長く保つことができます。
関節も筋肉も、「使いながら守る」ことが大切です。