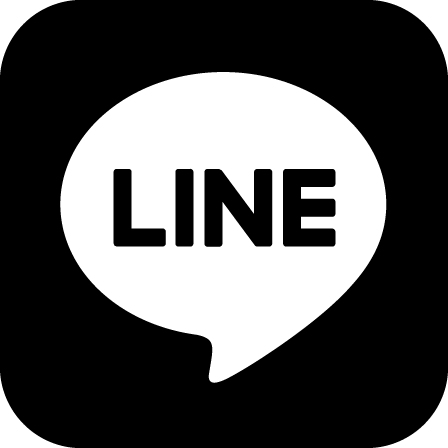私たちは日常生活の中で、肩こりや腰痛、頭痛など「痛み」を経験することがあります。痛みは単に体の不調を知らせるサインにとどまらず、実は集中力や記憶力といった「認知機能」にも影響を与えることが明らかになっています。
イギリスの研究チーム(Attridgeら, 2015)は、大規模な一般市民を対象に「痛みがどのように集中や記憶課題を妨げるのか」を調べました。ここで使われたのは「n-back課題」と呼ばれるテストです。画面に次々と出てくる文字や数字を見ながら、「何個前に出たものと同じかどうか」を判断するもので、注意力やワーキングメモリ(作業記憶)を測る代表的な方法です。
研究の内容
この研究には1318名もの成人が参加しました。研究者たちは、痛みがある人とそうでない人に同じ課題を行ってもらい、成績を比較しました。その結果、次のようなことが分かりました。
・痛みがある人は課題の成績が低下していた
・特に「間違っていないのに間違いだと思い込む(false alarm)」が増えていた
・痛みの強さが高い人ほど成績が悪くなる傾向があった
つまり、痛みは単に「不快」なだけでなく、注意や記憶の正確さを奪い、頭の働きを妨げることが示されたのです。
なぜ痛みが集中を妨げるのか?
痛みがあると、脳はそれに注意を向けざるを得ません。体を守るための自然な反応ですが、その分ほかの作業に割けるリソースが減ってしまいます。たとえば、腰痛が気になると会議に集中できなかったり、頭痛があると本の内容が頭に入らなかったりするのは、このメカニズムによるものです。
日常生活への影響
今回の研究で注目すべき点は、実験室ではなく「インターネットを通じて一般の人」に調査したことです。つまり、これは特別な環境だけでなく、普段の生活に近い状況でも痛みが認知機能を妨げるということを示しています。
現代社会では、仕事や家事、勉強などで集中力が求められる場面が多くあります。そこで慢性的な痛みを抱えていると、知らず知らずのうちに判断ミスが増えたり、仕事の効率が下がったりする可能性があるのです。
どう対策すればよいのか?
痛みをゼロにすることは難しいですが、以下の工夫で「痛みによる集中力の低下」を和らげられるかもしれません。
・こまめにストレッチや体操を取り入れる(血流を促し痛みを和らげる)
・適切な姿勢を保つ(腰痛や肩こりの予防につながる)
・痛みが強いときは無理に作業を続けず休む(集中できないときは効率も悪くなる)
・必要に応じて医療機関に相談する(慢性的な痛みは放置せず、専門的に対応することが大切)
まとめ
今回の研究は、「痛みは体の問題だけでなく、頭の働きにも悪影響を与える」ということを科学的に示しました。痛みを抱えながら「集中できない」「物覚えが悪くなった」と感じるのは気のせいではなく、脳の仕組みによるものです。
だからこそ、日常的なケアや体調管理がとても重要です。痛みを軽くすることは、同時に集中力や仕事のパフォーマンスを高める第一歩につながります。