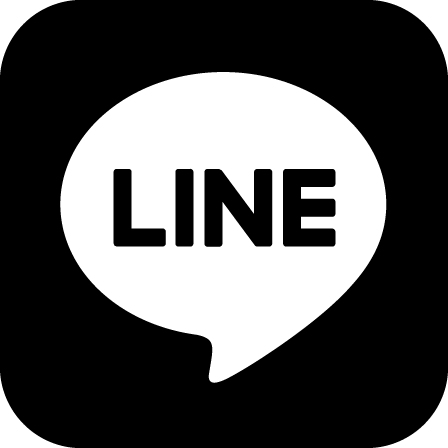普段の生活で「息が速くなって苦しい」と感じたことはありませんか?運動したとき、階段を駆け上がったとき、または不安や緊張で呼吸が浅く速くなったときなど、人はさまざまな場面で呼吸数が増えます。短時間であれば自然な反応ですが、この状態が長く続くと「呼吸筋」に大きな負担がかかり、筋肉が疲れてしまうことがあります。
呼吸筋とは?
呼吸は自動的に行われているため、あまり意識することはありませんが、実は多くの筋肉が関わっています。
主役は「横隔膜(おうかくまく)」というドーム状の筋肉です。横隔膜が上下に動くことで肺が広がったり縮んだりし、空気を出し入れしています。さらに肋骨の間にある肋間筋(ろっかんきん)、首の筋肉(胸鎖乳突筋や斜角筋)、お腹の筋肉なども呼吸をサポートしています。これらをまとめて「呼吸筋」と呼びます。
呼吸数が増えると何が起きる?
呼吸数が増えると、横隔膜や肋間筋がいつもより速く、何度も収縮と弛緩を繰り返さなくてはいけません。つまり「筋トレの回数が急に増える」ようなものです。普段よりも筋肉に酸素とエネルギーが必要になり、使いすぎるとだんだん疲れてきます。
特に浅く速い呼吸では、1回の呼吸でしっかり空気を取り込めないため、筋肉は「たくさん働いているのに効率が悪い」という状態に陥ります。結果として「息切れ」や「胸の疲れ」「呼吸が追いつかない感覚」につながりやすくなるのです。
呼吸筋が疲れるとどうなる?
呼吸筋が疲労してしまうと、体にさまざまな影響が出ます。
・息苦しさの悪循環
呼吸筋が疲れると呼吸の効率が下がり、さらに呼吸数が増える → さらに筋肉が疲れる…という悪循環に。
・姿勢への影響
呼吸を助けるために首や肩の筋肉を使いすぎると、肩こりや首のこりにつながります。猫背姿勢が強まる人も少なくありません。
・運動能力の低下
運動中に呼吸筋が疲れてしまうと、十分な酸素を取り込めず、筋肉や全身の持久力が落ちます。スポーツ選手だけでなく、日常生活での「階段を上るのがつらい」といった感覚にもつながります。
・全身の疲労感
呼吸は休むことができないため、呼吸筋が疲れると常にだるさや疲れを感じやすくなります。
予防・改善のためにできること
では、呼吸筋の疲労を防ぐにはどうすればよいのでしょうか?
1.ゆっくり深く呼吸する習慣を持つ
普段から意識的に「息を深く吸ってゆっくり吐く」練習をすると、横隔膜をしっかり使えるようになります。
2.軽い運動で心肺を鍛える
ウォーキングやストレッチなどの有酸素運動は、呼吸筋の持久力を高めます。
3.姿勢を整える
猫背や前かがみの姿勢は横隔膜や肋骨の動きを制限します。背筋を伸ばし、胸を開くようにすると呼吸が楽になります。
4.リラックスを意識する
ストレスや不安は呼吸数を増やす大きな原因です。軽いストレッチや瞑想などで心を落ち着けることも呼吸筋の負担軽減につながります。
まとめ
呼吸数が増えることは、一時的には体に必要な反応ですが、長く続くと呼吸筋に過剰な負担がかかり、疲労や息苦しさにつながります。普段からゆったりと深い呼吸を心がけ、呼吸筋を休ませる・鍛えることが大切です。
「なんとなく呼吸が浅い」「すぐに息が切れる」と感じる方は、もしかすると呼吸筋が疲れているサインかもしれません。ぜひ一度、ご自身の呼吸に意識を向けてみてください。