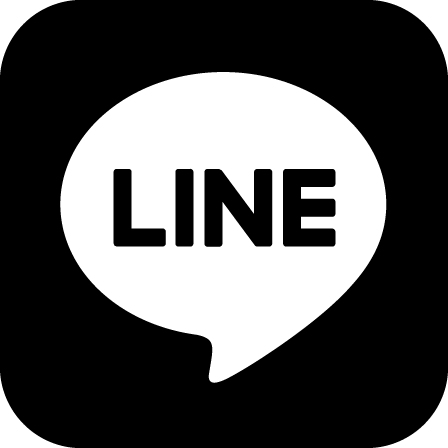私たちの体を動かすうえで大切な役割を果たしている関節。その中のクッションである「軟骨」が弱ってしまうと、痛みや動きにくさを引き起こす病気につながります。その代表的なものが「変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)」です。近年の研究では、この病気と「廃用性萎縮(はいようせいいしゅく)」との関係が注目されています。
変形性関節症とは?
変形性関節症とは、関節の軟骨がすり減り、骨が変形していく病気です。特に膝や股関節で多く見られ、中高年から高齢の方に多いのが特徴です。
進行すると「歩くと痛い」「立ち上がるのがつらい」「正座ができない」など、日常生活に大きな影響が出ます。厚生労働省の調査では、介護が必要になる原因の第1位が関節の病気とされており、社会全体にとっても大きな課題になっています。
廃用性萎縮が関節を弱くする
廃用性萎縮とは、体を使わないことで筋肉や軟骨が弱っていく現象です。長くベッドで寝たきりになったり、関節を動かさなかったりすると、軟骨が薄く弱りやすくなります。
問題は、この「弱った軟骨」が、普通の軟骨よりも負担に耐えられないことです。小さな衝撃や体重のかかり方でも傷つきやすく、結果的に変形性関節症へ進みやすい状態になってしまいます。
研究では、動物を使った実験で「動かさない期間を経て弱った軟骨」にケガを加えると、通常よりも関節症の進行が早いことが確認されています。つまり、廃用性萎縮は変形性関節症を早めるリスク因子になるのです。
「Pre-OA」という考え方
最近では「Pre-OA(プレ・オーエー)」という言葉も使われています。これは「まだ症状は出ていないが、変形性関節症の手前の状態」を指します。
廃用性萎縮で弱った軟骨は、このPre-OAとよく似た状態だと考えられています。痛みもなく、動作もできるけれど、軟骨はすでに脆くなっていて、そこに強い負担がかかれば関節症が発症してしまう…。このように「静かに進むリスク」を抱えた段階なのです。
日常生活で気をつけたいこと
入院やケガで長期間動かさなかったあとに、急に立ち上がったり歩いたりすると関節に大きな負担がかかります。特に高齢の方は注意が必要です。
だからこそ、リハビリや軽い運動を少しずつ取り入れて、徐々に関節に負担をかけることが大切です。また、普段から適度な運動を習慣にすることで、関節を「強い状態」に保ち、変形性関節症を防ぐことにもつながります。
まとめ
-
変形性関節症は、軟骨がすり減って関節が変形する病気で、多くの人が悩まされる。
廃用性萎縮によって軟骨が弱ると、変形性関節症に進みやすい。
廃用性萎縮は「Pre-OA(関節症の前段階)」にあたる可能性がある。
長期の安静後や日常生活では、急に負担をかけず、少しずつ動かすことが予防につながる。
「動かさないで弱る → 急に動かして壊れる」。この流れを防ぐために、関節も“使いながら守る”ことがとても大切です。